研究要旨「ドイツボードゲームの教育利用の試み」
皆さま、こんにちは。
TOKUZO WORKSスタッフのH.Sです。
本日は、行っている支援内容やワークショップに関して、エビデンス(根拠)になるような研究をご紹介させていただきます。
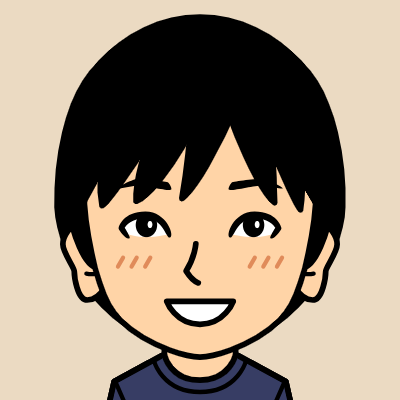
例えば、医療機関に行って
「治るかわからないけど、この治療法をやってみましょう!」と言われるのと、
「あなたの症状では、過去にこのような治療法に効果がありました。なので、この治療法をやってみましょう!」と言われるのでは、
その医療機関や治療方法における信頼感や治療に対する動機づけが全然違うのではないでしょうか? 福祉機関でもそれは同じことだと思っています。通所されるメンバーさんに対するプログラムには過去の研究から得られた知見を参考にする必要があると感じます。
今回紹介させていただくのはコチラ!
本日、紹介するのは「ドイツボードゲームの教育利用の試み―考える喜びを知り生きる力に結びつける―(2011)有田隆也 コンピュータ&エデュケーション 31 34-39」です。
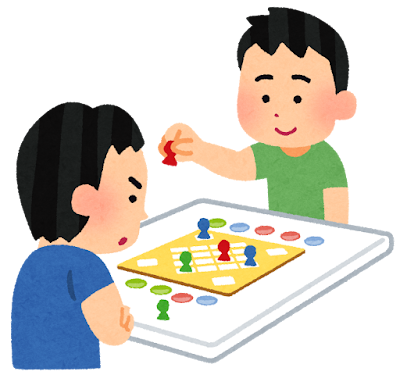
ドイツでは年間数百種類のボードゲームが新たに発売されており、そのテーマは多様で我々の生活における相互交流に影響を与えていると考えられています。ボードゲームは、思考を刺激し、参加しているプレイヤー同士のコミュニケーションを促進します。思考の基盤を醸成するいう意味では大変効果的であると考え、名古屋大学では1年制への教育課程において、ボードゲームを活用した授業を実施しました。
授業を受講した生徒の感想は以下のとおりです。
・戦略を考えたりすることは数学をとくように、とても 頭の体操になりました。
・他の講義では身につかないような推理力などがついて、とても充実した講義だと思います。
など、高評価を回答した生徒が多かったようです。
ボードゲームをプレイする効果とは?
我々の知能というものは、環境に上手に適応することができ、上手に利用することができるようになった結果が知能や心であるととらえてしまいがちですが、近年の研究では「社会的知能仮説」というものがあり、これは「複雑化する個体間の関係、社会的環境こそが、心や知能を作り上げた」とするものです。ボードゲームの多くは様々な社会的な状況や問題をテーマとして扱っているため、実際に社会に出てからの事前の予習となることや創造・想像力向上のための活動として効果があると考えられます。
刻一刻と変化する社会状況に適応していくことが求められていますが、ボードゲーム上ではより早く変化する盤上の状況に対応しなければなりません。
自立訓練にしても、就労移行にしても、将来的には社会に出て自立して生活するために非常に重要なチカラを醸成することができますので、是非とも一度体験してみてください!
下記の通り、戸田市精神保健福祉アナログゲーム交流会を実施します。チラシのメールにご連絡でも構いませんし、ホームページのお問い合わせをご利用いただいても構いません。精神疾患や発達障がいをお持ちの方やそのご家族、支援者の方や、支援に興味がある方などご参加いただければと存じます。

TOKUZO WORKSでは、いつでも相談を受け付けております。
戸田市内や近隣の市に在住の方で、生活リズムが整わない、就労に向けて活動したいけど、どうしたらいいかわからないなどお悩みをお持ちの方がいたら、是非ともお問い合わせください。
