研究要旨「生活習慣病の認知/行動療法」野崎剛弘/須藤信行 (2011) 心身医学51 (12)
皆さま、こんにちは。
TOKUZO WORKSスタッフのH.Sです。
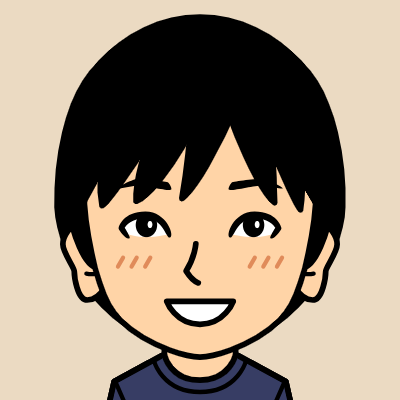
今回は、我々が行っている支援やプログラムに関して、エビデンス(根拠)になるような研究をご紹介させていただきます。 生活習慣病に対する心理療法の適用ということで、野崎剛弘氏・須藤信行氏の「生活習慣病の認知/行動療法」をご紹介させていただきます。
生活習慣病とは?
食生活の欧米化や生活リズムの多様性により、糖尿病や高血圧、肥満症、高脂血症など生活習慣が深く関与している疾患が急増しています。このような生活習慣病には、日常生活の仕方のみならず、その人個人の生きかたや価値観をも含んだ行動様式も含まれます。

生活習慣病の認知/行動療法の取り組み
体重の増加が見られる生活習慣病では、減量に主眼が置かれていることが多い。肥満に対する治療に関しては、食事療法・運動療法・薬物療法などが用いられ、そのエビデンス(根拠)がほぼ確立されています。しかし、減量後の再増加が問題視なるようになり、その過程で認知行動療法の応用が考えられるようになってきました。
行動変容のための治療技法としては、
1. セルフ・モニタリング
自分自身の現状を記録用紙やアプリなどを用いて記録をします。
2. ストレス・マネジメント
多大なストレスにより食生活が乱れることがあるため、ストレスを上手に管理する方法を学びます。
3. 刺激統制法
暴飲暴食などの不適応行動を起こしやすくする刺激を除去して、環境を整えます。
4. 反応妨害/習慣拮抗法
衝動的な欲求を我慢したり、欲求と両立しない行動をとることで欲求を処理します。
5.問題解決技法
ご自身が日々直面する様々な問題に対処することで、ストレス自体を減らすことができます。
6. 随伴性マネジメント
望ましい行動をとった際にご褒美を設定するなどして、治療へのモチベーションを高めます。
7. 認知再構成
不適切な考え方や物事の受け止めかたに対して、視野を広げたり、誰しもが保持している認知の歪みやクセを修正していきます。
8. ソーシャルサポート
社会的な支援ともいい、家族や友人、支援者などの存在そのものがモチベーションの維持に繋がります。
9. 再発防止訓練
今までの取り組みから、どのような場合に暴飲暴食をしてしまうのかなど、事前に対処をしておきます。
10. 目標設定
無理のない減量の目標設定や食事のカロリー設定などを行います。
11. 食行動修正
早食いなど満腹感に繋がりにくい食行動を修正することが食べ過ぎ防止になります。
上記のような方法をご本人の状態や状況を鑑みながら適応し、治療終結後もフォローアップを行うことで長期に効果が持続することがわかっています。

というような効果研究がなされています。 TOKUZO WORKS戸田公園では、上記のような技法を用いて精神疾患や発達障がいに親和性の高い生活習慣病を予防するための支援を行うことが可能です。
TOKUZO WORKS戸田公園では、いつでも相談を受け付けております。
戸田市内や近隣の市に在住の方で、生活リズムが整わない、就労に向けて活動したいけど、どうしたらいいかわからないなどお悩みをお持ちの方がいたら、是非ともお問い合わせください。
